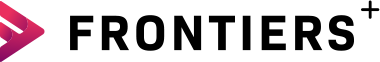iDeco(イデコ)はデメリットしかない?おすすめしない人の特徴やメリット・デメリットを解説
老後に年金だけで暮らしていけるかどうか不安に感じている方は多いでしょう。
そこでおすすめできるのは「iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)」という制度なのですが、この制度に関しては「デメリットしかない」とか「やらない方がいい」と感じる方もいます。
iDeCoの重要性や実用性について理解するためには、年金面だけでなく「節税」としてのメリットが大きいことや、他の投資方法と比較した場合のデメリット、さらにはNISAとの違いについても知る必要があります。
今回は加入を検討している方だけでなく、ネガティブな印象をお持ちの方に向けて、iDeCoという制度を改めて身近に感じられるように、わかりやすく解説していきます。
目次
iDeco(イデコ)のデメリットや注意点
次はiDeCoのデメリットや注意点について、5つの点をそれぞれ解説していきます。
のデメリット-1-min-1024x576.png)
元本保証がない
iDeCoには元本保証がありません。
元本変動型の商品は元から元本保証がありませんが、受け取り時に元本をそのまま受け取ることができる「元本確保型」に関しても、中途解約することで元本割れする可能性はあります。
ただし元本割れするリスク自体は元本確保型の方が低いため、低リスク運用を最重要視する方は元本確保型がおすすめです。
大きく投資することができない
iDeCoは加入者の保険種別によって拠出額に制限があるため、大きな金額を投資することはできません。
たとえば個人で株式投資を行う場合、資金を際限なく投資に回すことが可能であり、さらに「レバレッジ」によって保持資金より多くのお金を投資することもできます。
iDeCoはそのような「リターン優先」の運用ができないため、「リスクを許容して大きな利益を得る」ことを目標とする人には向いていません。
逆に、投資初心者であり可能な限りリスクを追わずに資産運用したい方はiDeCoで投資信託を選択することをおすすめします。
お金が受け取れるのは原則として60歳から
iDeCoは原則途中解約できないため、60歳になるまで受け取ることができません。
特別な条件付きで解約することも可能ですが、以下の要件を満たす必要があります。
- 加入者が死亡した場合(死亡一時金)
- 加入者が高度障害状態になった場合(障害給付金)
- 一定の条件を満たした場合(脱退一時金)
3つ目の脱退一時金に関する「一定の条件」とは、次のとおりです。
- 60歳未満の企業型DC未加入者である
- 保険料免除者である
- 障害給付金を受給していない
- 積立期間が1ヶ月から3年以下である
- 積み立てた金額が25万円以下である
- 企業型DC脱退(資格を喪失した日)から2年以内である
以上の条件を「すべて」クリアできる場合のみ、「脱退一時金」を受け取って途中解約が可能です。
他の投資方法のように好きなときにやめたり、お金を引き出したりできないので注意しましょう。
口座開設や維持に手数料がかかる
iDeCoは拠出金だけでなく、次に挙げる3つの手数料が発生します。
- 加入手数料:一律2,829円
- 口座管理手数料:171円から(金融機関により異なる)
- 信託報酬:商品により異なる
加入手数料に関しては一度だけ発生しますが、口座維持手数料と信託報酬に関しては継続的に発生するコストです。
月々数百円の違いでも年数が増えると大きな違いになるため、可能な限り低い手数料で維持できる証券会社を選ぶことをおすすめします。
受け取り方法によっては所得税が課せられる
すでに解説したように、iDeCoは受け取り方によって「雑所得」か「退職所得」のどちらかとなり、異なる所得控除が適用されます。
一時金で受け取る場合は退職所得控除の額が少なくなったり、年金の場合は受け取る度に手数料が発生するなど、それぞれに異なるデメリットがある点にも注意が必要です。
iDeco(イデコ)のメリット
次はiDeCoのメリットについて、6つの点をそれぞれ解説していきます。
のメリット-min-1024x576.png)
運用の手間がかからない
iDeCoは個人投資で資産運用をするよりも、簡単に運用できます。
投資信託を選択すれば、複数の金融商品が組み合わされたファンドを、自分のニーズに合わせて選ぶことができるからです。これにより、初心者でも簡単に分散投資が可能です。
また株式投資のように、価格変動を常に監視している必要はありません。投資のプロが市場の動きに合わせて運用してくれるからです。これにより投資経験や知識の浅い初心者が資産を大きく失うリスクも軽減されます。
月々5000円から始められる
たとえば株式投資は最初から数十万円を用意しなければならないケースが多いですが、iDeCoは月々「5,000円」程度の少額から始められるのもメリットです。
場合によっては1,000円から始められる商品もあります。拠出金を増やしたい場合も、年1回に限り変更が可能です。
掛金が全額税控除の対象になる
iDeCoでは、毎月の掛金が全額所得控除となります。
もちろん控除となるのは拠出限度額範囲内となりますが、これにより所得税・住民税の両方が節税できます。
運用益は全額非課税になる
iDeCoの運用によって発生した運用益は、全額非課税になります。
iDeCoでなければ「20.315%」という高い税金が課されるため、この点はiDeCo特有の大きなアドバンテージとなります。
受け取る際にも控除を受けられる
iDeCoで積み立てたお金は60歳以降に受け取ることができますが、受け取り方によって異なる税制優遇が適用されます。
- 一時金として受け取る:退職所得控除
- 年金として受け取る:公的年金等控除
どちらを選ぶかは人それぞれですが、会社員として長年働いていた方は分離課税になる一時金として受け取ることで、退職所得控除額が増えるためお得です。
それぞれの働き方やニーズに応じて受け取り方を決定しましょう。
転職時にはiDeCoから企業型確定拠出に移管できる
すでにiDeCoに加入している方が転職した場合、転職先の企業に企業型確定拠出年金(企業型DC)があれば、iDeCoで積み立てた資産を移管することが可能です。
これにより、iDeCoの資格は喪失することになります。
ただし自動的に移管されるわけではなく、転職先での事務手続きや、iDeCoの運営管理機関へ「加入者資格喪失届」を提出する必要があります。
ちなみに転職先に企業型DCがある場合もiDeCoを継続できますが、被保険者の種別および登録事業所の変更手続きをする必要があります。
それぞれの立場ごとに異なる処理および必要な手続きに関しては、以下の表をご参照ください。
| 想定されるケース | 詳細と必要事項 |
| iDeCoから企業型DCに移管 | iDeCo加入資格を喪失 加入者資格喪失届を提出 転職先で手続き |
| iDeCoを継続 | iDeCoの加入資格は継続 被保険者種別の変更手続き 登録事業所の変更手続き |
| 第1・3・4号保険加入者が転職 | 国民年金の種別が変更 加入者被保険者種別変更届を提出 |
| 第2号加入者が転職 | 加入者被保険者種別変更届を提出 |
ちなみにiDeCoと企業型DCを併用する場合、会社が設定する拠出額に上乗せできる「マッチング拠出」は利用できないため、注意が必要です。
iDeco(イデコ)とは
iDeCoとは「個人型確定拠出年金」のことです。
個人型確定拠出年金とは、60歳以降に受け取れるようになる国民年金にくわえて、個人が任意で加入できる年金制度です。国民年金と大きく異なるのは、自分で金融商品を購入し運用することで利益を出す、という点です。
次はiDeCoの仕組みについて解説していきます。
加入対象者
iDeCoの加入対象者は、以下のいずれかに当てはまる人です。
- 国民年金第1号被保険者(自営業者等)
- 国民年金第2号被保険者(厚生年金被保険者)
- 国民年金第3号被保険者(専業主婦・専業主夫等)
- 国民年金任意加入被保険者
上記のとおりiDeCoに加入するためには、必ず国民年金制度に加入している必要があります。
さらに加入している国民年金の種類ごとに、次に挙げる基本的要件を満たしている必要があります。
| 国民年金の種類 | 加入条件 |
| 第1号被保険者 (自営業者) |
満20〜60歳未満である 農業者年金に未加入 国民年金で全額・半額免除を受けていない |
| 第2号被保険者 (会社員・公務員) |
65歳未満である 会社員で企業型DC加入者は以下の2点を満たしていること ①掛金が毎月定額拠出である ②マッチング拠出を利用していない |
| 第3号被保険者 (第2号被保険者) |
65歳未満である |
| 第3号被保険者 (専業主婦・主夫) |
満20〜60歳未満である |
iDeCoへの加入を検討している方は、自分が上記いずれかの条件をクリアしているか、改めて確認してみましょう。
拠出限度額
iDeCoの拠出限度額は、加入者がどの国民年金に加入しているかによって、異なります。
以下の表をご覧ください。
| 国民年金の種類 | 1ヶ月あたりの拠出限度額 |
| 第1号被保険者 | 68,000円 |
| 第2号被保険者 | 他の制度に未加入:23,000円 企業型DCのみ加入:20,000円 確定給付型のみ・確定給付型と企業型DCに加入:12,000円※1 公務員・私立学校教職員共済制度に加入:12,000円 |
| 第3号被保険者 | 23,000円 |
| 第3号被保険者 | 68,000円※3 |
※1 事業主掛金と合算したとき月27,500円を上回ることはできない
※2 配偶者の他制度掛金と合算で月55,000円または27,500円を上回ることはできない
※3 付加保険料を納付している場合は控除して限度額を計算する
iDeCoの加入を検討している方は、自分がどのグループに属しており、月間・年間いくらまで拠出できるのか改めて確認しておきましょう。
運用方法
iDeCoの運用方法は、基本的に次の2つの種類に分けられます。
- 元本確保型:元本が保証されている商品
- 元本変動型:元本が保証されていない商品
まず元本が保証されている商品の代表例は「保険」および「定期預金」です。それに対して元本が保証されていないのが「投資信託」です。
投資信託では、一例として次に挙げるような商品で構成されたファンドを購入することで、初心者でも簡単に分散投資できます。
- 日本株式・先進国株式・新興国株式
- 日本債券・先進国債券・新興国債権
- 国内不動産・海外不動産
元本確保型・元本変動型それぞれ異なる特徴やメリット・リスクの両方を理解したうえで、どちらを選ぶか決めましょう。
iDeco(イデコ)はどんな人に向いている?
次はiDeCoが向いている人と向いていない人の特徴について解説していきます。
iDeco(イデコ)が向いている人
iDeCoが向いている人は、次の3ついずれかに当てはまる人です。
- 老後資金を貯めたい人
- 難しい投資は避けたい人
- 自営業者(第1号被保険者)の人
老後資金を貯めたい人
iDeCoは老後資金を「十分に」貯めたい人に向いています。
国民年金にプラスする形で老後にまとまったお金を受け取ることができますし、所得控除などの税制優遇も受けられるからです。
そもそもiDeCoへの加入を検討している多くの方は「国民年金」だけでは老後の生活が不十分であることを危惧していますが、同時に「貯蓄」だけで老後資金を用意することの難しさも理解しています。
積み立てたお金を途中で引き出せないからこそ、自分で行う貯金よりも強制力のあるiDeCoに加入するのは、合理的な判断だといえます。
難しい投資は避けたい人
投資に「難しさ」を感じる人もiDeCoがおすすめです。
投資信託を活用すれば運用方法を自分で考える必要なく、投資に関わることのほぼ全てをプロに一任できるからです。
同様の理由で、今まで投資に触れたことがない、関わったことがない方もiDeCoがおすすめです。
自営業者(第1号被保険者)の人
特定の企業に属していない個人事業主は厚生年金に加入できません。
そのため自分で国民年金制度に加入することで老後に備える必要がありますし、ボーナスや退職金などのまとまったお金も受け取れません。
その点、自らの裁量で老後資金を用意できるiDeCoへの加入は大きなメリットがあります。
掛金は全額所得控除になりますし、運用益も税金が発生しません。受け取りに関しても節税効果が高いことから、厚生年金に加入できない分をiDeCoによって十分カバーできます。
むしろ個人事業主やフリーランスなどの「将来が確約されていない」立場の人こそ、iDeCoに加入するメリットは大きいといえます。
iDeco(イデコ)が向いていない人
iDeCoが向いていない人は、次の3つのいずれかに当てはまる人です。
- 大きなリターンを得たい人
- 好きな時にお金を引き出したい人
- 元本保証が欲しい人
大きなリターンを得たい人
iDeCoは安定性よりも高いリターンを期待する人には向いていません。
そもそもiDeCoは「個人型確定拠出『年金』」であるため、お金稼ぎのための制度ではありません。あくまで国民年金だけでは不足する老後資金をカバーするための仕組みです。
投資は常にリスクとリターンがトレードオフの関係にあり、株式投資やFXなど一定以上のリスクを許容できる方法ほど高いリターンを期待できます。
資金が十分にあり、ある程度のリスクを許容してでも効率的に資産を増やしたい方は、iDeCo以外の方法で資産形成することをおすすめします。
好きな時にお金を引き出したい人
iDeCoによる資産形成は「積み立て」と表現されるため誤解されがちですが、60歳までは解約できないという仕組み上、好きなときにお金を引き出すことはできません。
銀行口座のように扱えないため、自由にお金を出し入れしたい人には向いていません。
元本保証が欲しい人
iDeCoでもっともおすすめできるのは投資信託ですが、投資信託には元本保証がないため、元本が最終的に戻ってくることを最優先に考えている方にはおすすめできません。
すでに解説したように保険や定期預金などの「元本確保型」でも、100%元本が保証されるわけではない点に注意が必要です。
iDeCo(イデコ)を始めるのにおすすめのネット証券3選
次は、これからiDeCoへの加入を検討している方におすすめできる3つのネット証券について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説していきます。
①手数料がお得な「SBI証券」

| 新規口座開設時の手数料 | 2,829円 |
| 口座維持・管理手数料 | 171円 |
| 取扱商品数 | 元本変動型:37 元本確保型:1 |
| 対象ファンド | 国内株式 国際株式 国内債権 国際債券 国内REIT 国際REIT バランス型 コモディティ 定期預金 年金保険 |
| 信託報酬 | 0.09372%以内~2.124%程度 |
おすすめポイント
- 15年以上の運営実績
- 2種類の手数料が無料
- 多様な商品ラインナップ
株式会社SBI証券の「SBI証券」は、とにかく低コストで運用したい方におすすめです。
初期コストは国民年金基金連合会に支払われる「2,829円」のみであり、口座開設手数料だけや管理手数料も国民年金基金連合会および信託銀行に支払われるもの以外は発生しません。
商品数も豊富であり、国内外の株式や債権、REITやバランス型にくわえてコモディティも用意されています。
②楽天ポイントが貯まる「楽天証券」

| 新規口座開設時の手数料 | 2,829円 |
| 口座維持・管理手数料 | 171円 |
| 取扱商品数 | 元本変動型:31 元本確保型:1 |
| 対象ファンド | 国内株式 国際株式 国内債権 国際債券 国内REIT 国際REIT バランス型 コモディティ ターゲットイヤー型 定期預金 |
| 信託報酬 | 0.09889%~1.70500% |
おすすめポイント
- 低コスト・長期運用のために厳選された商品
- 運営手数料は無条件でずっと無料
- 楽天銀行を指定するとハッピープログラム対象
楽天証券も初期コストおよび運用コストを抑えられる証券会社です。
口座開設時は国民年金基金連合会への「2,829円」しか発生せず、運営手数料も規定の料金以外は発生しません。
商品は低コスト・長期運用に適した、厳選された32本の中から選ぶことができます。
また掛金引落口座に楽天銀行を指定するとハッピープログラムの対象となり、楽天ポイントを貯めることができます。普段から楽天のサービスをフル活用している方に、特におすすめできます。
③サポートが手厚い「松井証券」

| 新規口座開設時の手数料 | 2,829円 |
| 口座維持・管理手数料 | 171円 |
| 取扱商品数 | 元本変動型:39 元本確保型:1 |
| 対象ファンド | 国内株式 国際株式 国内債権 国際債券 国内REIT 国際REIT バランス型 コモディティ ターゲットイヤー型 定期預金 |
| 信託報酬 | 0.09889%~1.70500% |
おすすめポイント
- 創業100年に渡る実績
- 各種手数料が無料
- 業界最高水準となる計40種類の商品に対応
証券会社として古い歴史を持つ「松井証券」は、低コストと商品の豊富さをどちらも優先される方におすすめです。
手数料および取扱商品数どちらも業界最高水準であり、多様な商品が用意されています。
公式ホームページ上では加入診断にくわえて節税シミュレーションも用意されており、松井証券に加入するかどうかに関わらず、誰でも簡単に利用できます。
iDeco(イデコ)に関するFAQ
最後は、これからiDeCoに加入する方が疑問を抱きがちな、3つの質問に回答します。
iDeco(イデコ)の掛け金は5000円や1万円だと意味ない?
答えは「いいえ」です。iDeCoの掛金はたとえ5,000円や1万円でも問題ありません。
なぜなら掛金が少なくても、拠出できる範囲内で確実に老後のための資金形成ができますし、拠出額の大小に関わらず節税のメリットを享受できるからです。
たとえば、30歳からiDeCoに加入した自営業者が、毎月5,000円の掛金で「3.0%」の運用利回りを実現できた場合について、松井証券の「iDeCoシミュレーター」を用いてシミュレーションしてみます。
- 65歳に一時金で受け取る場合の金額:3,707,818円
- 年金として20年間受け取る場合の月々の金額:185,391円
- 節税できる所得税・住民税の総額:420,000円
- 非課税になる運用益の総額:321,564円
このように、拠出額が少なくても早めに始めることができれば、老後に毎月18万円程度の年金を受け取れる計算となります。
そのため可能な限り早めに始めれば、たとえ拠出可能な金額が少なくても老後の生活を豊かにすることが可能ですし、節税も可能です。
iDeco(イデコ)は途中解約できる?
答えは「いいえ」です。iDeCoは少なくとも60歳までは拠出を続ける必要があり、特別な理由がない限り途中解約できません。
すでに解説したように、本人が死亡した場合や高度障害状態になった場合など、途中解約は「特例」でしか認められません。
大前提として、iDeCoに加入するなら60歳までは続けることを想定しておきましょう。
iDeco(イデコ)とNISAの違いは?
iDeCoではなくNISAへの加入を検討している方もいるでしょう。この2つの制度には、次のような違いがあります。
| iDeCo | NISA | |
| 目的 | 老後のための資産形成 | 資産形成 |
| 節税面 | 運用益が非課税 掛金が全額所得控除 受け取り時に税制優遇 |
運用益のみ非課税 (年間120万円まで) |
| 受取時期 | 60歳以降 | 商品の売却時 |
どちらも国が制定した資産運用制度であり、運用益非課税という点が共通しています。
ただしiDeCoが「年金を補う」目的であるのに対して、NISAは老後に関わらず個人の投資活動および資産形成を促すための制度です。
実はこの2つは「どちらかを選べば良い」というものではなく「併用することで真価を発揮するもの」なのです。
iDeCoとNISAどちらにも拠出限度額が設定されていますが、併用することで単純に積み立てられる金額が増えます。
会社員の場合、iDeCoだけだと最高で月23,000円までしか拠出できませんが、NISAを併用すると月々の拠出額を少なくとも10万円以上引き上げられます。
より効率的に資産形成したい方は、iDeCoとNISAの併用をおすすめします。
まとめ
将来受け取れる年金額に不安を感じているなら、すぐにでも少額から「iDeCo(個人型確定拠出年金)」を始めてみるのはいかがでしょうか。
あくまで年金制度であるため貯蓄が続けられない方にもおすすめできますし、「月々5,000円」を用意するだけで資金形成と節税を両立し、自分は「確実に将来に備えている」という安心感も得ることができるからです。
◎関連記事